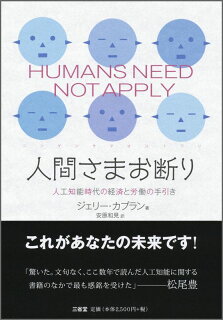NHKのEテレで放送されている「人間ってナンだ?超AI入門シーズン3」。
現代は「IT×●●」というように、あらゆるものにITが入っている時代です。
そして、人工知能(Artificial Intelligence)の進化・発展に伴い、近未来は様々な分野で「AI×●●」となっていくと私は考えています。
だからこそ、多くの人がAIの最低限の知識と理解をしておくべきではないでしょうか。
この番組では、AI技術の紹介、また実際の活用事例なども取り上げられていて、超AI入門というように非常にわかりやすく面白い番組ですので、毎回備忘録的に記事として残しています。
シーズン3では、実践編。第1回のテーマは「会話する」です。
日本ではスモールデータの活用がキーワード
GAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)と呼ばれるアメリカの大企業がこぞってビッグデータを蓄積しています。
日本企業はなかなかこういった企業に太刀打ちできないと考えられる一方で、99.7%が中小企業の日本ではスモールデータの活用がキーワードだと冒頭ありました。
PoC(Proof of Concept:概念実証)でとりあえずやってみるということを通して、
現場で使えるように、また売上があがっていくように
そういった取り組みが活発になっていくフェーズに入ってきているそうです。
気楽に、気軽に、話すことができるAI
今回のテーマが「会話する」ということですが、会話を可能にするAIがどんどん増えてきていますね。
人間は、他人に直接愚痴を言うことができなくても、AIアカウントに対しては簡単に言えます。
そう考えると、会話をするのは人でなくてもいい?ということが挙げられますよね。
会話が成立し、自分のことを理解してくれるのであれば、それは人でなくてもいい・・・
結果としてAIへの依存性が高くなってくるという問題も含みつつも、
世の中的には話し相手になってくれ、自分のことを理解してくれるAIの存在がニーズとして増えてきているのかもしれません。
言葉の奥にある思考やイメージ、経験、哲学
3年分くらいのデータがあれば、その人の特徴をデジタル上で作り上げられるという推測があるそうですね。
今の時代は、SNSを通して多くのデータがあふれていますし、
その人のチャットやメッセンジャーのやりとりから語尾の特徴などを学習し、その人のように会話してくれるというのは確かに技術的に可能だなと感じました。
ただ、人の言葉は、人生経験のあらゆるものが複合的になって発せられるものです。
口調を真似る、言いそうなことを予測するといったことを、限りなく近しいようにAIで作ることはできたとしても、
本当にその人が言うことをAIに言わせるというのは非常に難しいですね。
出てくる言葉は氷山の一角であり表面的です。
その裏、その奥にある思考やイメージ、経験、哲学など全てが詰まったものが、結果として言葉となって出てきます。
AIは人間をどこまで理解できるのでしょうか。
また、「不気味の谷」という言葉が出てきました。
私は初めて聞いた言葉でしたが、面白い表現ですね。
番組で紹介されていたAIを使ったデジタルクローン。
こういったAIは、近すぎるけど何か違う、その人が言いそうなことだけど何か心が入っていない。
会話における「不気味の谷」を超えられるかどうかというのが大きなポイントみたいです。
この「不気味の谷」を超えられるかどうかで、その人らしさというのを人間が感じられるようになってくるわけですね。
AIは心を持てるのか?
人間に大事なのは”共感能力”だというコメントもありましたが、どこまで相手のことを理解し、共有共感できるのかというのは、本当に難しいことだと思います。
例えば、「暗いね」という言葉の奥には、電気をつけたいと言う意味なのか、ただ共感してほしいだけなのか、というのがありますね。
「人間に言葉が与えられたのは互いの考えを隠すためである」
18世紀 フランス革命時代の外交官 政治家 タレーラン(1754-1838)
こんな言葉が紹介されていましたが、
言葉というのは本当に偉大な発見でありつつも、多くの意味を含んでいるんだなと改めて思います。
人間は、自律性を持つことで、隠し事をするようになったのでしょうか。
そして、どこか相手に自分の全てを悟らせないようにしているのでしょうか。
人間が何気なくやっている会話をAIに置き換えるという試み。
これから、会話の分野についてはどんな進化発展があるか期待です!
感想
現代人は、リアルなコミュニケーションが減ってきています。
気楽に・気軽に話すことができるという面や、話すきっかけを作るという意味では、AIの活用は進んでいくかもしれませんね。
しかし、現代社会では人間関係は切っても切り離せられないと思います。
AI依存で人間が人間らしさを失っていっては本末転倒だなと感じました。
また、非言語的な要素との出会いができるのかということがこれからももっともっと研究されていったら良いなと個人的には感じました。
AIは意味を理解しません。価値を理解しません。
人間は、一つひとつの出会いにどんな意味・価値を創造するのか。
日常生活の中であらゆるものと会話していきながら、こんなことを考えてみたいと思います。
オススメ図書
番組にも出演されている東京大学の松尾教授の講演をお聞きした際に、人工知能関連の推薦図書が紹介されていました。
私もこれらの図書を通して、一般的な知識は身についたと思っていますので、興味のある方はぜひお手にとってみてください。
・入門書として
・読み物として